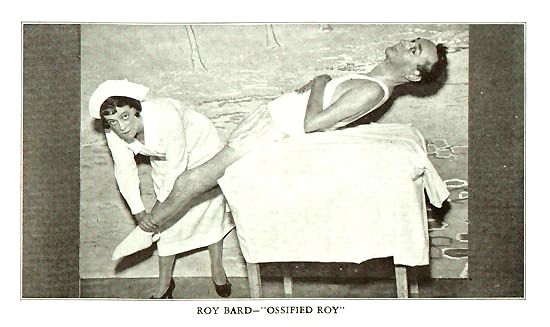娯楽殺人映像 - スナッフ・フィルムは実在するか
1970 - 80 : モキュメンタリーとスナッフ
こうしてスナッフ・フィルムは未だ誰もその実体を見ぬまま、都市伝説のようにその存在だけが語られることとなった。「まだ誰も見ていないが、どこかにあるらしい」そのフィルムの噂は、70年代から80年代にかけてピークに達したのである。一方、映画業界は逆にその伝説にあやかる形で、"実際の殺人"を宣伝文句とする映画をこぞって制作した。それら作品は、当時はその都度熱狂を持って迎えられ、人々の間に「次こそは本物のスナッフ・フィルムか」という期待を生んだ。それはあたかも、"殺人映像"というタブーに魅了された映画業界が、人々の熱狂と共謀して本物の"スナッフ・フィルム"が登場するのを、心待ちにしていたかのようでもあった。以下は当時、実際の"死"を描いた(と宣伝された)代表的な作品群である。
Faces of Death - ジャンク 死と惨劇
 1978 年、ジョン・アラン・シュワルツ(John Alan Schwartz)監督(クレジットはConan le Cilaire)。パラシュート事故や動物が屠殺される様子、解剖の様子や殺人事件など、様々な本物の死の場面を集めたセミ・ドキュメンタリ作品。ただし死の瞬間を写した映像は少なく主に死体の映像が中心である(さらに有名な電気椅子処刑シーンなど一部はやらせもある・写真)。残酷極まりないその描写から、40カ国以上で放映が禁止されたが、日本では大々的に公開され(邦題は『ジャンク死と惨劇』)、大きな反響を呼んだ。映画自体はモンド的ではあるものの、取材による映像は少なく、主に世界から集めた映像の編集によって構成されていた点で、旧来的なモンドとは異なっていた。
1978 年、ジョン・アラン・シュワルツ(John Alan Schwartz)監督(クレジットはConan le Cilaire)。パラシュート事故や動物が屠殺される様子、解剖の様子や殺人事件など、様々な本物の死の場面を集めたセミ・ドキュメンタリ作品。ただし死の瞬間を写した映像は少なく主に死体の映像が中心である(さらに有名な電気椅子処刑シーンなど一部はやらせもある・写真)。残酷極まりないその描写から、40カ国以上で放映が禁止されたが、日本では大々的に公開され(邦題は『ジャンク死と惨劇』)、大きな反響を呼んだ。映画自体はモンド的ではあるものの、取材による映像は少なく、主に世界から集めた映像の編集によって構成されていた点で、旧来的なモンドとは異なっていた。
もともとはイタリア制作の作品として公開されたが、実際には日本の制作会社が、米国の制作会社に出資して委託制作されたものであることが、後に明らかになっている(これは先の 釣崎氏のインタビューでも触れられた通り、当時、日本でいかに死体映像作品の人気が高かったかを物語っている)。また監督含め、クレジットされている人物はほとんどが偽名、もしくは実在に見せかけた架空の人物(解説のフランシス・ B・グロス博士など)で、これはシャクルトン同様、単に作品を"裏流出"映像的に見せるため(=権威付ける為に)プロダクションが行ったプロモーション戦略であると言われる。
Cannibal Holocaust - 食人族
 1980年、ルッジェロ・デオダート(Ruggero Deodato)監督。アマゾン上流で消息を絶った米国のドキュメンタリー取材班の足跡を辿って、捜索に向かったモンロー博士が、遺体と共に発見された未開封のフィルムを発見。帰国したモンロー博士がフィルムを見るとそこには、四人が現地で"ショッキングな"ドキュメンタリーを撮るため、演出の名のもとにやらせや蛮行を繰り返し、終いには原住民の怒りを買って全員が惨殺される様子の一部始終が納められていた。
1980年、ルッジェロ・デオダート(Ruggero Deodato)監督。アマゾン上流で消息を絶った米国のドキュメンタリー取材班の足跡を辿って、捜索に向かったモンロー博士が、遺体と共に発見された未開封のフィルムを発見。帰国したモンロー博士がフィルムを見るとそこには、四人が現地で"ショッキングな"ドキュメンタリーを撮るため、演出の名のもとにやらせや蛮行を繰り返し、終いには原住民の怒りを買って全員が惨殺される様子の一部始終が納められていた。
この作品は当時、実際に起きた事件の映像、との触れ込みで宣伝されたことから、再び大きな話題を呼んだ。有名な「串刺し女」のシーンを始めとする残酷さ加減もさることながら、メタ・ドキュメンタリ的に作り込まれたストーリーも巧妙であり、現代と未開地を往来するモンド的な構成とスナッフ的な宣伝手法、さらにスプラッター的なショッキングさを見事に総合した傑作であった(※6)。しかし作品はその度を超えた生々しさが徒となり、フランス、イタリア、イギリス等で「"スナッフ・フィルム" なのではないか」といった懸念を生み、当時は(あるいは今でも)実際にそう信じ込んだ者も多かった。
 その結果、イタリアでは上映開始から四週間足らずで動物虐待を理由に上映が禁止され(生きた亀が甲羅を剥がされる" 本物の"シーンがあった)、最高裁で猥褻物という判決が与えられてしまった。またイギリスでも上映が禁止され、海賊版が没収された際に、「これはスナッフ・フィルムである」という確認判決がなされた(しかしこれら欧州諸国での騒動がかえって人々の興味を引き、日本では大成功を納めている)。
その結果、イタリアでは上映開始から四週間足らずで動物虐待を理由に上映が禁止され(生きた亀が甲羅を剥がされる" 本物の"シーンがあった)、最高裁で猥褻物という判決が与えられてしまった。またイギリスでも上映が禁止され、海賊版が没収された際に、「これはスナッフ・フィルムである」という確認判決がなされた(しかしこれら欧州諸国での騒動がかえって人々の興味を引き、日本では大成功を納めている)。
※6.デオダート監督が巧妙であったのは、実は本編中に、一部本物の処刑映像を混入させていたことである。それは殺された取材班が最初に撮影した『地獄への道』というフィルムに納められたアフリカの銃殺シーンで、彼ら取材班のやり方に辟易していたモンロー博士らはそれを見ながら「これもやらせ」と断罪する。しかし、その映像はデオダート監督が現実の報道映像から引用した、本物の射殺映像だったのである。つまりここでは、本物の死体映像とフィクション(食人族の映像)が多重的に倒置されている。本物をあえてやらせといい、やらせを本物として見せることで、鑑賞者や批評家の死(の映像)に対する鈍感さを皮肉ったわけである。
Guinea Pig - ギニー・ピッグ
 1985 年、日本のギニー・ピッグ・レーベルより発表された全七作の残酷ホラー作品。都市伝説としてのスナッフ・フィルム的世界観を下敷きに、当時の特撮技術を駆使してリアルな惨殺シーンを作り上げた。中でも数多くの話題を呼んだのは第二作『ギニー・ピッグ2血肉の華』(日野日出志監督)である。映画はまず「この映画は、ある日、監督(日野日出志)の元に送られてきた猟奇殺人の8mmフィルムと54枚の写真を元に再現した"セミドキュメント"である」という注意書きから始まる。そして続く本編は、夜道で拉致された女性がベッドに縛りつけられ、ネオ・ジャポニズム的な雰囲気の暗い密室で甲冑を身に纏った侍に惨殺されるというものであった(ちなみにその"元の8mm"の映像は、エンディング・ロール時に流れ、その真偽も話題を呼んだ)。
1985 年、日本のギニー・ピッグ・レーベルより発表された全七作の残酷ホラー作品。都市伝説としてのスナッフ・フィルム的世界観を下敷きに、当時の特撮技術を駆使してリアルな惨殺シーンを作り上げた。中でも数多くの話題を呼んだのは第二作『ギニー・ピッグ2血肉の華』(日野日出志監督)である。映画はまず「この映画は、ある日、監督(日野日出志)の元に送られてきた猟奇殺人の8mmフィルムと54枚の写真を元に再現した"セミドキュメント"である」という注意書きから始まる。そして続く本編は、夜道で拉致された女性がベッドに縛りつけられ、ネオ・ジャポニズム的な雰囲気の暗い密室で甲冑を身に纏った侍に惨殺されるというものであった(ちなみにその"元の8mm"の映像は、エンディング・ロール時に流れ、その真偽も話題を呼んだ)。
この作品が際立って話題になったのは、その徹底したリアルな残酷描写もさることながら、フィルムを巡って起きた幾つもの事件であった。米国でこの作品を見た俳優のチャーリー・シーンが、これを本物のスナッフ・フィルムと勘違いし、MPAA(米映画協会)に連絡、FBIと日本の当局が調査に乗り出すというそれ自体都市伝説のような事件が発生した(捜査直後、SFX作品であることがすぐに判明し、収束)。
また1992年には、米国からこのビデオを取り寄せた英国の男性が、スナッフ・フィルムと勘違いした税関の通報を受け、逮捕されるという事件が起きた。裁判ではこのフィルムが作り物であることがすぐに判明したが、男は他にも幾つかの医学解剖系のフィルム等を輸入しており、面倒を避けようとしたためか、さっさと「スナッフ・ビデオを入手しようとしていた」ことを認めたため、有罪判決を受け、罰金を支払うハメになったのだった。
 これらの事件自体は茶番劇であり、大きな意味はない。しかし、問題はその後のマスコミの反応であった。なぜならば、もはやギニー・ピッグが本物であったかどうかといった事は事件を報じる記者 - そして詳細には無関心な大衆 - には関係なく、「チャーリー・シーンがスナッフ・フィルムを通報した」、「スナッフ・ビデオを輸入した男に罰金刑」などと大々的に報じられたため、結果的にはスナッフ・フィルムの実在性を強く印象づけたからである。
これらの事件自体は茶番劇であり、大きな意味はない。しかし、問題はその後のマスコミの反応であった。なぜならば、もはやギニー・ピッグが本物であったかどうかといった事は事件を報じる記者 - そして詳細には無関心な大衆 - には関係なく、「チャーリー・シーンがスナッフ・フィルムを通報した」、「スナッフ・ビデオを輸入した男に罰金刑」などと大々的に報じられたため、結果的にはスナッフ・フィルムの実在性を強く印象づけたからである。
これはまさに映画スナッフの時と同じ構図だった。つまり例え映画が作り物であろうと、"スナッフ・フィルム"という言葉がメディアに乗る度、"スナッフ・フィルム"がどこかに存在するらしい、という大ざっぱな印象だけがいたずらに誇張され、それが都市伝説としてのスナッフ・フィルムを更に補強するというわけである(※7)。
※7.日本では、1989年連続幼女誘拐で逮捕された宮崎勤がこのビデオを所有していたことから、猟奇殺人者に影響を与えたビデオとして、槍玉に上げられた。その結果、ギニー・ピッグ・シリーズは発禁処分に追い込まれ、その後は米国やドイツから DVDボックスが再発、逆輸入される形で販売されるという不遇が続いた。しかし2006年には日野監督自身の解説付きで劇場で再上映されている。
THE MAN BEHIND THE SUN - 黒い太陽731
 1988年、。牟敦芾監督(香港)。日中戦争における関東軍石井731部隊の行ったと言われる人体実験等をスプラッター風に描いた作品。その残酷描写はまた徹底しており、氷付けの手に熱湯をかけて肉を丸ごとはぎ取る、ガス室に親子を閉じこめて殺す、減圧室に男を閉じこめ肛門から脱腸させる、ネズミ数百匹を(本当に)一気に焼き殺すといった惨たらしいシーンがひたすら続く。この映画が特に話題になったのは、少年の解剖シーンである。
1988年、。牟敦芾監督(香港)。日中戦争における関東軍石井731部隊の行ったと言われる人体実験等をスプラッター風に描いた作品。その残酷描写はまた徹底しており、氷付けの手に熱湯をかけて肉を丸ごとはぎ取る、ガス室に親子を閉じこめて殺す、減圧室に男を閉じこめ肛門から脱腸させる、ネズミ数百匹を(本当に)一気に焼き殺すといった惨たらしいシーンがひたすら続く。この映画が特に話題になったのは、少年の解剖シーンである。
公開当初から、その余りにもリアルな映像から実際の死体が使われているのではないかという噂を呼んだが、後に監督その事実を認めた。監督によれば、撮影中、病院に少年の死体を"予約"し、死者が出たタイミングで、実際に死体を入手して死体解剖を行ったのだという(また実験で死んだ遺体が次々と焼却炉に放り込まれるシーンでも、実際の遺体が使われていたのではないかといった噂が流れたがこの真偽は不明)。なおこの映画については反日プロパガンダ作品と評されることもあるが、突き抜けた残酷描写の衝撃性はもはやその主題さえ忘れさせ、モンドや、エクスプロイテーション作品として認識されることも多い。
- T. F. MOUS - THE MAN BEHIND THE SUN
- Amazon.co.jp 黒い太陽七三一戦慄! 石井細菌
このように70年代から80年代中頃にかけては、映画『スナッフ』の成功を皮切りに、死体映像や"本当の殺人シーン"を売り物にしたエクスプロイテーション映画が数多く登場した。それはさも死体を求める食人族さながらに、人々が"本物の死体映像"を見るために劇場へと足を運ぶ、奇妙な熱気に包まれた時代だった。しかしこの時代、数多く作られたこれら作品が実際のところ如何なるものであったかは、多分、シャクルトンのこの一言に集約されている。「あの殺人が本当だとしても、それを認めるほど俺はバカじゃないし、うそだとしても、それを認めるほどバカじゃないよ」。
- 前の記事:"死体なき国の死体写真家" -- 釣崎清隆インタビュー
- 次の記事:男性の顔色が真っ青になる 米
- この記事のカテゴリ:MEDIA
- X51.ORG HOME / X51.ORG ARCHIVES
NEWS HEADLINE
TOP STORIES
ARCHIVES
X51.ORG
CATEGORY
- ART
- BLOW
- CRIME
- DISASTER
- EDGE
- GHOST
- LIFE
- LOVE
- MEDIA
- MEDICAL
- NEWS
- OPARTS
- PHALLIC
- PSYCHIC
- RELIGION
- SCIENCE
- UFO
- UMA
- X-FILES
- X51